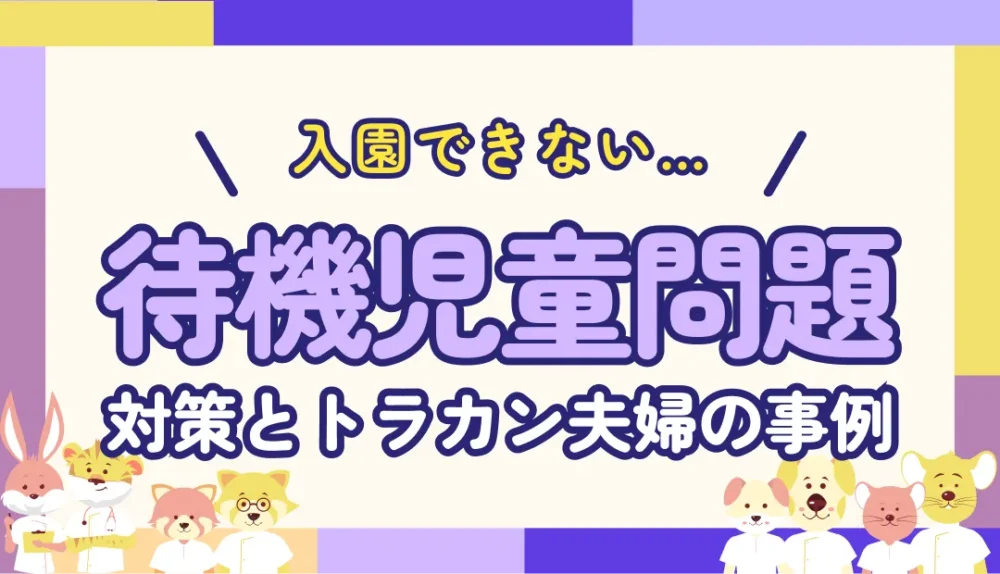保育園・幼稚園・認定こども園の違いは?子育てナースなら保育園の理由を体験談込みで解説
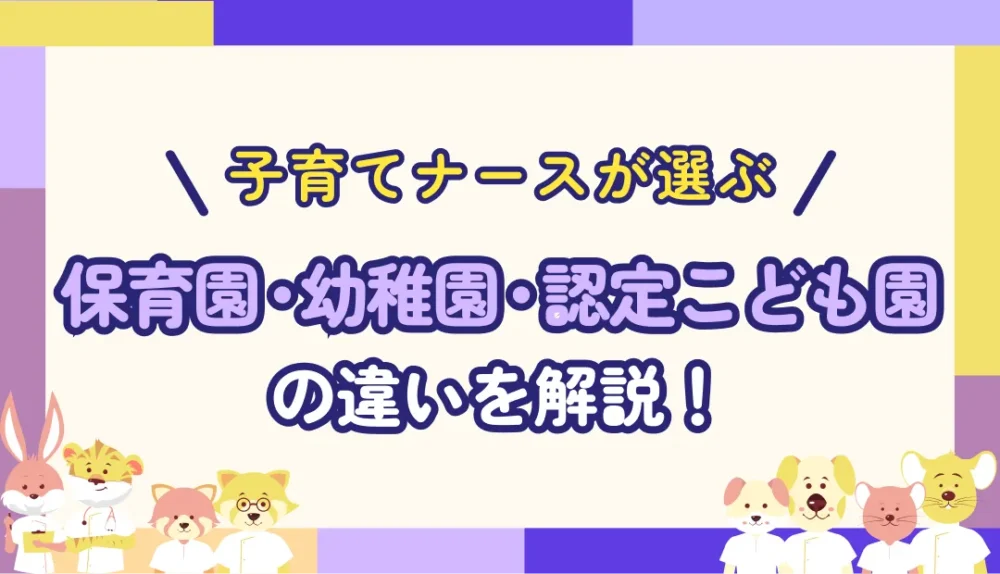
こんにちは、トラカンです!
早速いですが、子どもの入園でこんな悩みを抱えていませんか?
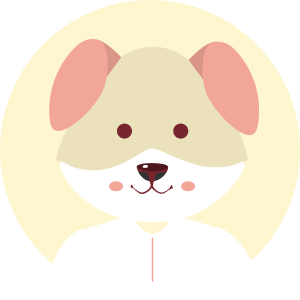
保育園と幼稚園・認定こども園の違いがわからない
何を基準に選べばいいの?
子育てをしながら働くナースなら、どれを選ぶべき?
現状に合わせた入園先を選べないと、子育てと仕事の両立がハードモードになります
ですが、各園の違いはわかりづらく、選べないと悩む子育てナースも少なくありません
実際、私たち看護師夫婦も入園前は同じ悩みを抱えていました
そこで本記事では、次のポイントを中心にお話しします
- 結論、子育てナースなら「保育園」or「こども園」
- 保育園・幼稚園・認定こども園の違い
- 最近の保育施設の傾向
- その他の保育施設(待機児童の間)
自分に合った入園先を選べると、保育料の負担や送迎の問題も解決します
看護師と子育ての両立もかなり楽になります
記事の最後には、待機児童中でも通える園もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください!
【比較表】保育園・幼稚園・認定こども園の違い
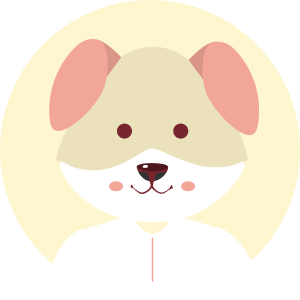
保育園と幼稚園の違いはなんとなくわかるけど、認定こども園は全くわからない…
そんな人のために、3施設の違いを比較できるように、一覧表にまとめました
保育園・幼稚園・認定こども園の違いは、以下の通りです
| 項目 | 保育園 | 幼稚園 | 認定子ども園 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 保護者が働いている間の「保育」 | 子どもに教育を提供する「教育施設」 | 保育と教育の両方を兼ね備えた施設 |
| 管轄 | 厚生労働省 | 文部科学省 | 内閣府(認定)+各自治体(運営) |
| 対象年齢 | 0歳〜小学校入学前まで | 満3歳〜小学校入学前まで | 0歳〜小学校入学前まで(園によって異なる) |
| 保育時間 | 8時間以上 | 4〜6時間程度(延長保育あり) | 利用区分(※1を参照)により異なる |
| 利用条件 | 保護者の就労など「保育の必要性」が必要 | 誰でも通える(制限なし) | 保護者の就労など「保育の必要性」が必要 |
| 保育料 | 世帯所得に応じた応能負担 | 私立は園ごとに異なる/公立は一律 | 利用区分により異なる |
| 利用のしやすさ | ◯:夜間・病児保育など対応型の保育園もある | △:延長保育だけだと限界 | ◯:園により柔軟対応可能 |
結論、子育てナースなら「保育園」or「こども園」
保育園やこども園の方が、仕事と両立しやすいです
なぜなら、幼稚園と比べて預かってもらえる時間が長いからです
保育園やこども園は延長保育を使えば最長で19時まで預かってもらえいます
一方の幼稚園は「9:00〜14:00」と短く、預けられる人も限られます
送迎時間も含めると幼稚園では仕事との両立は難しいでしょう
ただし、最近だと幼稚園に子どもを預ける人も増えてきました

理由については、次の見出しで解説するよ
保育園・幼稚園・こども園の違いはなくなりつつある
近年、保育施設ごとの違いはなくなってきています
その背景には、共働き世帯の増加による長時間の預かりニーズが高まったことがあげられます
こうした流れを受けて、各施設では預かり時間が徐々に延長されてきました

利用料金は違いますが、朝から夕方まで預かってもらえる施設が増えました
例えば、幼稚園は本来、短時間の教育が基本です
しかし、延長保育を利用すれば、最長18:30まで預けられます
ただし、無償化の対象は「保育の必要性があると認められた場合」に限られます
そして、無償化には上限金額が設けられています
次に、各保育施設の具体的な特徴を見ていきましょう
保育園の特徴
保育園は、児童福祉法に基づき厚生労働省の管轄で設置された施設です
共働き家庭や仕事を持つ保護者のために、子どもを預かる福祉施設として設置されました
以下の特徴について見ていきましょう
- 対象児童
- 給食の有無
- 保育料
対象児童
対象児童は、0歳から就学前までの乳児および幼児です
フルタイムで働いている親が利用し、7:30〜18:00頃まで預かってもらえます

保育指数(保育園に入るための点数)が高い人が優先的に入れます
給食の有無
給食の提供は義務です
つまり、親がお弁当を作る必要はありません
料金の設定は運営する自治体によって違います
例えば、「主食が4,000円、副食が3,000円」や「副食のみ4,000円で主食は無料」といったケースがあります
保育料
無償化の対象は、以下の通りです
- 住民税非課税世帯の0〜2歳児
- すべての世帯の3〜5歳児
また延長保育の保育料は、運営する自治体によって異なります
例えば、1時間あたり200円の料金体系や、時間に関係なく1回あたり1,000円といった例があります
延長保育における無償化の範囲は、以下の通りです
- 月額11,300円が上限
- 満3歳児かつ保育の必要性があると判断される非課税世帯は月額16,300円が上限
ただし、それを超える利用料については全額自己負担です
幼稚園の特徴
幼稚園は学校教育法に基づくき設置された文部科学省が管轄の保育施設です
就学前の子どもに教育を中心とした成長環境を提供する学校施設として設置されています
つまり、位置付けは学校(教育機関)です
以下の特徴について見ていきましょう
- 対象児童
- 給食の有無
- 保育料
対象児童
対象となるのは、満3歳〜小学校入学までの幼児です
主に専業主婦や、昼までの勤務など保育の必要性が比較的少ない家庭を想定しています
給食の有無
任意であり、各幼稚園に委ねられています
そのため、お弁当のところもあれば、給食を提供している施設もあります

幼稚園+延長保育で利用していた友人は、お弁当が大変という理由で、院内保育に変更していました
保育料
無償化の対象となる幼児は、以下の通りです
- 住民税非課税世帯の0〜2歳児
- すべての世帯の3〜5歳児
無償化の対象は保育料であり、延長保育料や給食費、行事費、送迎バス代などは自己負担です
延長保育における無償化の範囲は、以下の通りです
- 月額11,300円が上限
- 満3歳児かつ保育の必要性があると判断される非課税世帯は月額16,300円が上限
ただし、それを超える利用料については全額自己負担です
最近の幼稚園では、預かり時間終了後の午後2時以降に、園内で習い事(課外教室)を実施するところもあります
息子が通っていた幼稚園では、体操教室や英語教室、音楽教室などがありました
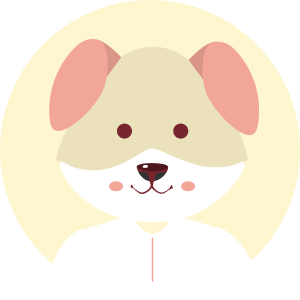
預かってくれている間に習い事までしてくれるのは、本当にありがたいですね
認定こども園の特徴
認定こども園は内閣府の管轄のもと、子育て支援を総合的に提供する施設です
施設の成り立ちは、保育園と幼稚園の機能である保育と教育を一体化です
以下の特徴について見ていきましょう
- 認定こども園の種類
- 対象児童
- 給食の有無
- 保育料
認定こども園の種類
認定こども園が制度化された背景には、待機児童問題があります
これを受けて、2016年(平成28年)に子ども・子育て支援法に基づき、認定こども園が誕生しました
認定こども園には、以下の種類があります
- 幼保連携型
- 幼稚園型
- 保育園型
- 地方裁量型
対象児童
対象児童は、0歳〜就学前までです
保育に欠けるか欠けないかに関わらず、受け入れが可能です

つまり、親の就労状況は入園条件に影響しないということです
ただし、実際は就労状況による保育点数が高い家庭から優先的に入園できます
私の住んでいる町は待機児童が溢れており、こども園に入るだけで1年半かかりました…
給食の有無
義務です
ただし、こども園を運営する地方自治体によって料金が異なります
例えば、私の住む地域では以下の通りです
- 教育部分を利用する3歳以上の子どもについては、給食費(主食費・副食費)や行事費などの実費は無償化の対象外
- ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもや、第3子以降の子どもについては、副食費が免除される場合がある
保育料
無償化の対象となる幼児は、以下の通りです
- 住民税非課税世帯の0〜2歳児
- すべての世帯の3〜5歳児
延長保育における無償化の範囲は、以下の通りです
- 月額11,300円が上限
- 満3歳児かつ保育の必要性があると判断される非課税世帯は月額16,300円が上限
ただし、それを超える利用料については全額自己負担となり、無償化の対象外となります
保育園・幼稚園・こども園以外の6つの保育施設【待機児童中の方へ】
この章では、保育園・幼稚園・こども園以外の保育施設を6つ紹介します
- 施設1:病院運営の院内保育・託児所
- 施設2:地域型保育事業(小規模保育など)
- 施設3:企業主導型保育施設
- 施設4:認可外保育施設(無認可保育施設)
- 施設5:病児・病後児保育施設
- 施設6:夜間保育施設
保育園・幼稚園・こども園以外の選択肢も持っておきたい方は、必ずチェックしてください!
施設1:病院運営の院内保育・託児所
院内保育は、仕事と育児の両立に悩むナースにとって最も身近な選択肢です
職場内にあるため、送迎時間がかかりません
夜勤明けや残業までした日勤などヘトヘトになった時、すぐに迎えができるのは体力的に嬉しいです
特に24時間対応型であれば、夜勤シフトにも柔軟に対応してもらえます
保育者と職場が連携しやすく、急な勤務変更にも対応しやすいのが強みでしょう
また、子どもを近くで預かってもらっている安心感もあります
施設2:地域型保育事業(小規模保育など)
地域型保育は、0〜2歳児を対象に少人数で手厚い保育を受けさせられる施設です
保育士との距離が近く、子ども一人ひとりに寄り添った対応をしてもらえます
我が子に手厚い保育を受けさせたい方は、地域型保育事業が良いでしょう!
また、不規則な勤務が原因で、看護師は育児に不安を感じやすいです

だからこそ、家庭的な雰囲気の中で子どもが育つという安心感は、大きな支えとなります
特に、ワンオペ気味のママナースにとっては、相談しやすい環境が心強い味方となるでしょう
施設3:企業主導型保育施設
企業主導型保育は、柔軟な運営体制が特徴の保育施設です
従業員の働き方に柔軟に対応しながら、認可保育所と同等の保育を受けられます
また、勤務先に関係なく地域住民の利用を許可している施設もあります

例えば、時間や曜日の融通が利きやすく、土日祝や夜間保育にも対応しています
子育てナースにとっては、シフトに合わせた保育が可能なため、制度の柔軟さが大きな魅力になるでしょう
また、保育料も比較的安価で、登録しやすい点もメリットと言えます
施設4:認可外保育施設(無認可保育施設)
認可外保育施設(無認可保育施設)とは、児童福祉法に基づく認可を受けていない保育施設のことです
院内保育所やベビーホテル、居宅訪問型保育(ベビーシッター)などが含まれます
これらの施設は、保育時間や受け入れ年齢の自由度が高いのが特徴です
また、突発的な勤務変更にも対応しやすい施設が多くあります

子育てナースにとっては、認可施設に空きがない状況でも利用できる「最後の砦」として機能します
そのため、職場を離れずに働き続けるためのセーフティーネットとなっています
施設5:病児・病後児保育施設
病児・病後児保育とは、病気の子どもを一時的に預けられる保育施設のことです
どうしても休めない日や、急な欠勤を避けたい時に、病気の子どもでも預かってもらえるため、子育てナースの強い味方となっています
看護師は責任ある職業であるため、休みを取りにくい立場にいるママナースも多いです
病院併設なら送迎時間が短縮でき、緊急時にはすぐに子どものもとへ駆けつけられる安心感があります
また、家族に頼れない状況でも「働き続ける選択肢」があることは、大きな安心材料となっています
お住まいの地域の病院併設以外の病児保育は、全国病児保育協議会のホームページで探せます

また、病児保育について詳しくは、病児保育とは?メリット・デメリットや利用の流れをわかりやすく解説【※子育てナース必読】で解説しています
参考:内閣府/病児保育事業
参考:全国病児保育協議会/加盟施設一覧
施設6:夜間保育施設
夜間保育施設は、夜勤を含むシフト勤務に対応した数少ない選択肢です
夕方から深夜、場合によっては早朝まで対応してくれます

夜間勤務が必須のナースにとって非常にありがたい存在です
昼間の保育園と併用できるケースもあり、24時間体制で子どもを預けることも可能です
また、「育児でお金が必要だけれど、子どもが小さいため夜勤はできない」と悩む子育てナースにとって、夜勤を続けるための有効な手段となっています
同僚への申し訳なさから夜勤免除を申請できない人もいますが、夜間保育を利用すれば解決します
夜間保育については、夜間保育は子育てナースの強い味方|夜勤や残業なんて怖くない働き方も実現可で解説しています
保育施設に関するよくある4つの質問
保育施設に関するよくある質問を4つ紹介します
- 質問1:無償化の対象は何歳から?
- 質問2:延長保育料は無償化の対象に入りますか?
- 質問3:認可外保育施設等は無償化の対象になりますか?
- 質問4:兄弟が多いと保育料の減額はありますか?
質問1:無償化の対象は何歳から?
無償化の対象は、以下の条件に当てはまる幼児です
- 3〜5歳児は、すべての家庭ですべての対象施設が無償
- 0〜2歳児は、住民税非課税世帯は無償
質問2:延長保育料は無償化の対象に入りますか?
延長保育(預かり保育)は、下記条件に当てはまる範囲内は無償化です
- 月額11,300円が上限
- 満3歳児かつ保育の必要性があると判断される非課税世帯は月額16,300円が上限
上限を上回る利用の時は追加の保育料が発生します
保育料については、各自治体で異なるため、あらかじめ確認しておきましょう
質問3:認可外保育施設等は無償化の対象になりますか?
保育園や認定こども園、幼稚園、企業主導型保育事業所の在園児が認可外保育施設を利用した場合、無償化の対象外になります
認可外保育施設とは、以下の施設のことです
- 認可外保育施設
- 病児保育
- ファミリー・サポートセンター事業 など
質問4:兄弟が多いと保育料の減額はありますか?
保育料の軽減措置をしている地方自治体もあります
ただし、地方自治体ごとに内容が違うため、詳細については市区町村に確認してください!
まとめ:家庭の状況に合わせて最適な保育施設を選ぼう!
今回は、保育施設の違いや特徴について見てきました
預かり時間や費用の面では、保育施設ごとに細かな違いがありました
一方で、近年そうした違いが少しずつなくなる傾向にあります
共働きの夫婦が増えており、長時間預かってくれる保育施設の需要が高まっているためです

その影響で、幼稚園でも保育園と同じ時間まで預かる「延長保育」を行うようになってきたよ
また、院内保育などの企業主導型保育施設や、認可外保育施設など、働き方に合わせた保育施設も登場しています
仕事と育児の両立が難しい看護職にとって、保育施設の選択肢が広がったのは嬉しいこと!

私も以前は「育児短時間勤務×院内保育」の組み合わせで、仕事と子育ての両立ができていました
なお、育児短時間勤務については、時短勤務は子育てナースの必須条件!メリデリや申請前の注意点を押さえて上手に活用しようで解説しています
それぞれの家庭で状況は異なります
ぜひこの記事を参考に、自分に合った保育施設を選んでみてください!
今回紹介した以外にも、子育てナース真の悩みは色々あります
読者様からいただい悩み相談を中心に、さまざまな悩みを記事にしていこうと思います
ぜひ、他の記事も読んでみてください!
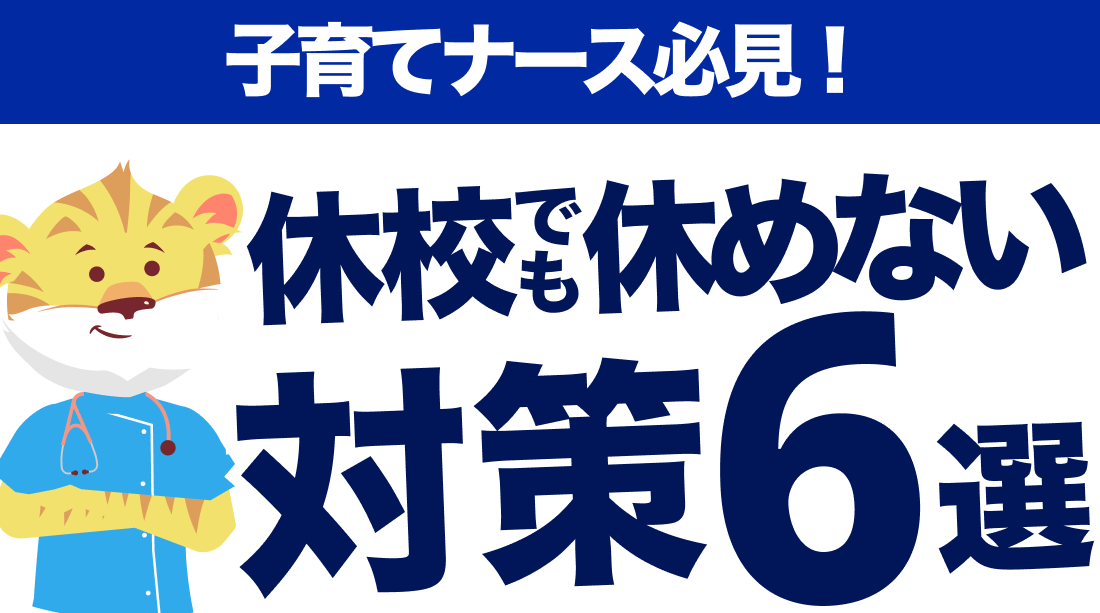
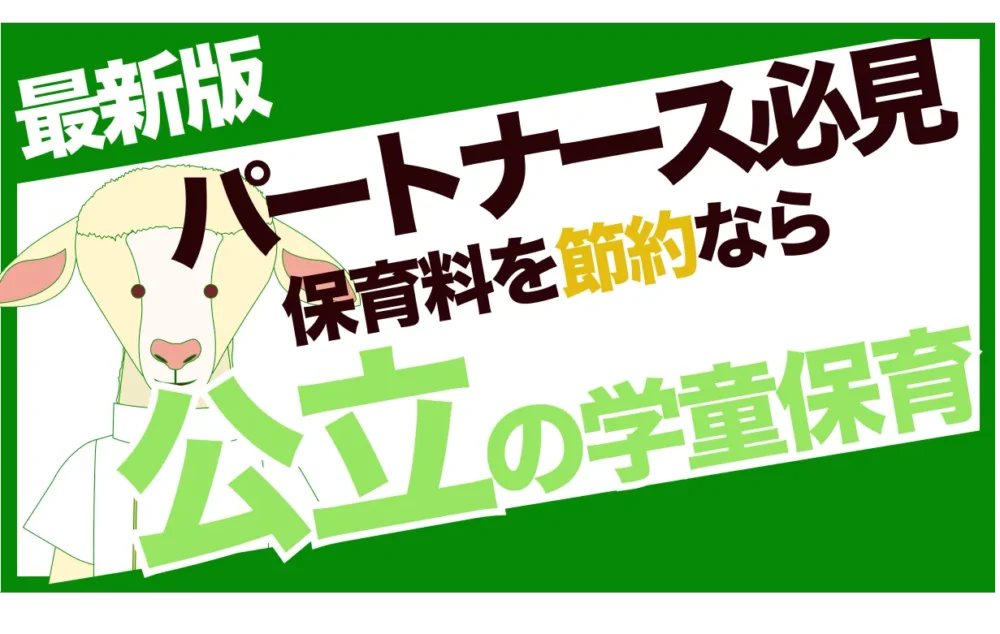
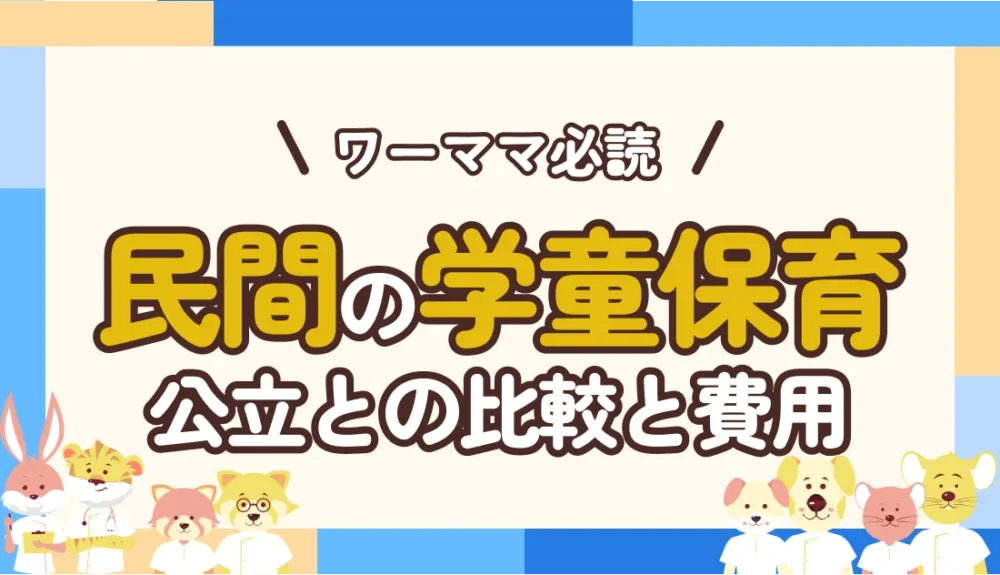
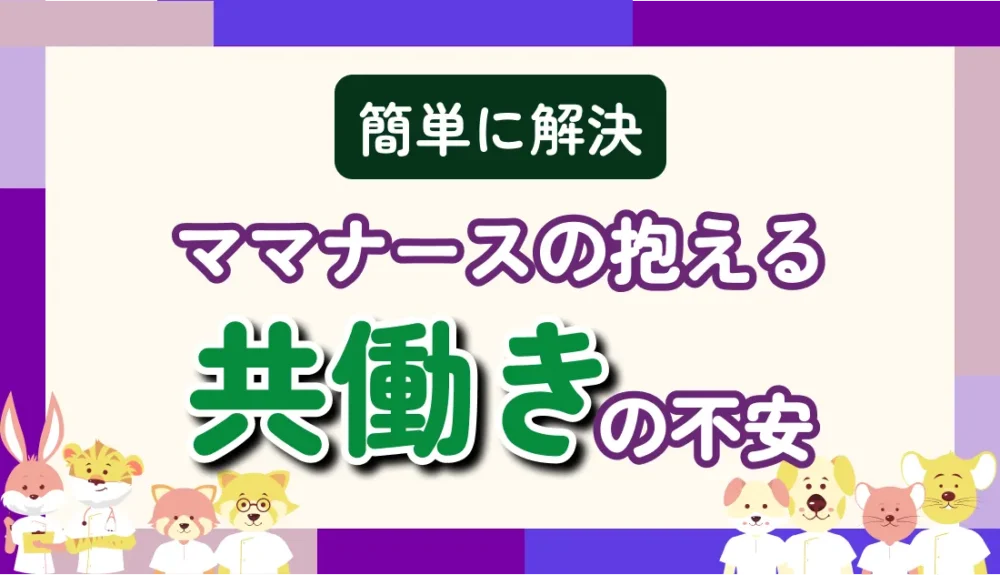
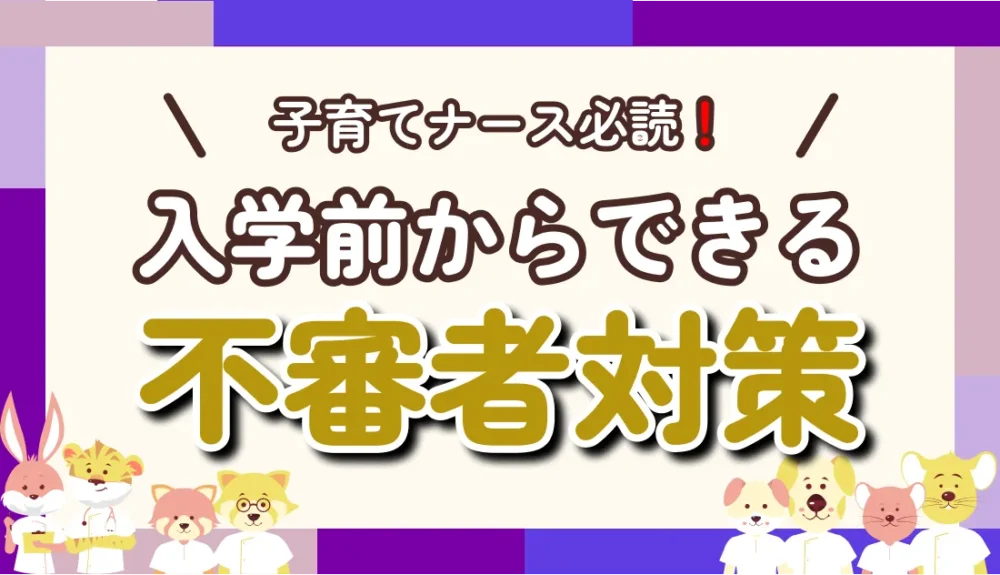
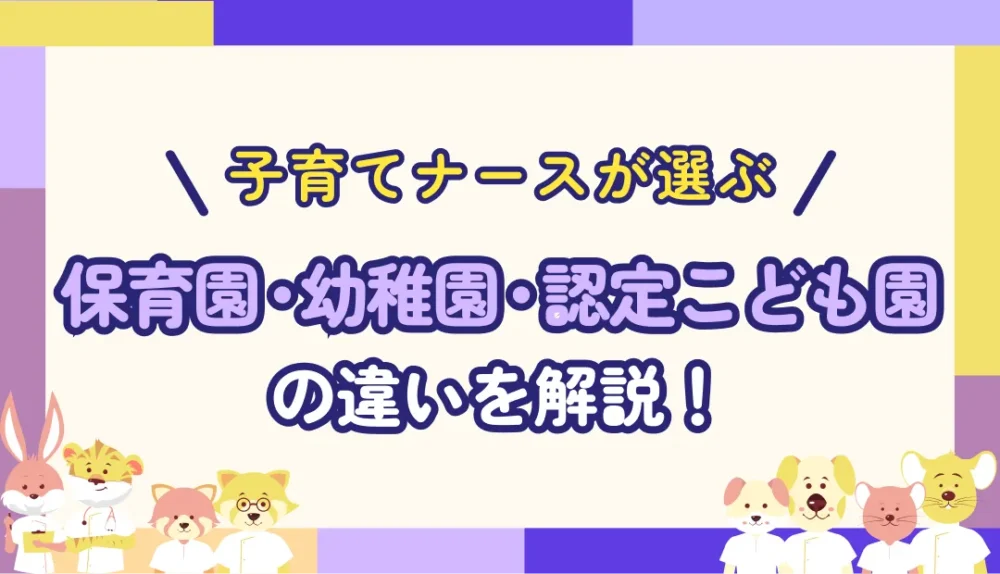
X(旧Twitter)でも共有してくれるとトラカンが喜びます✨