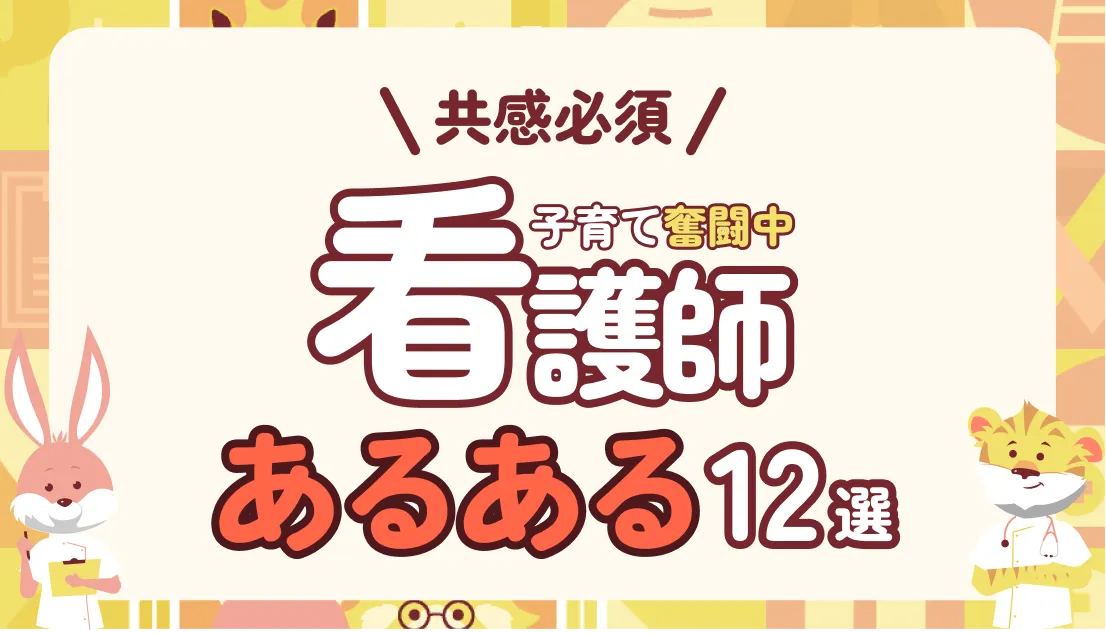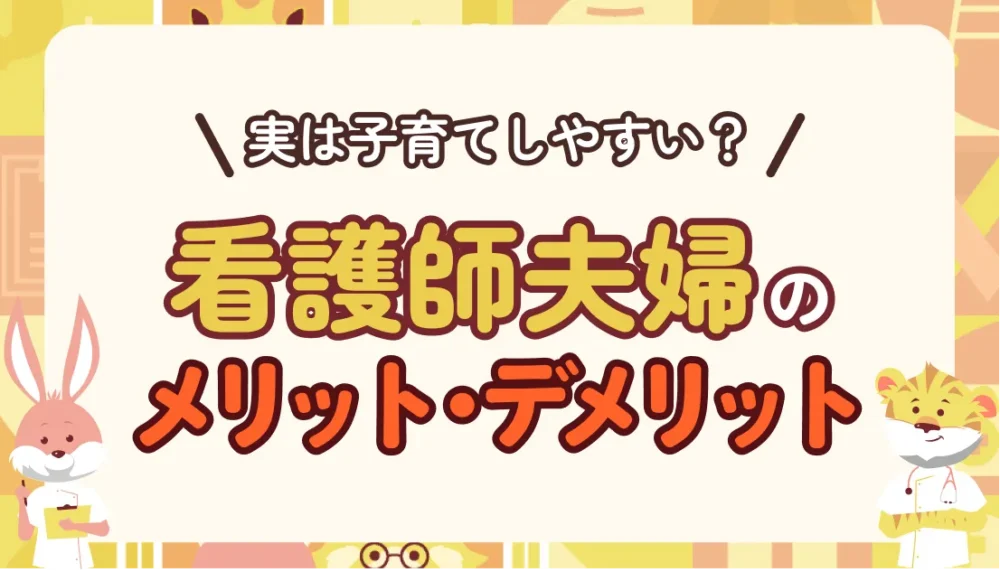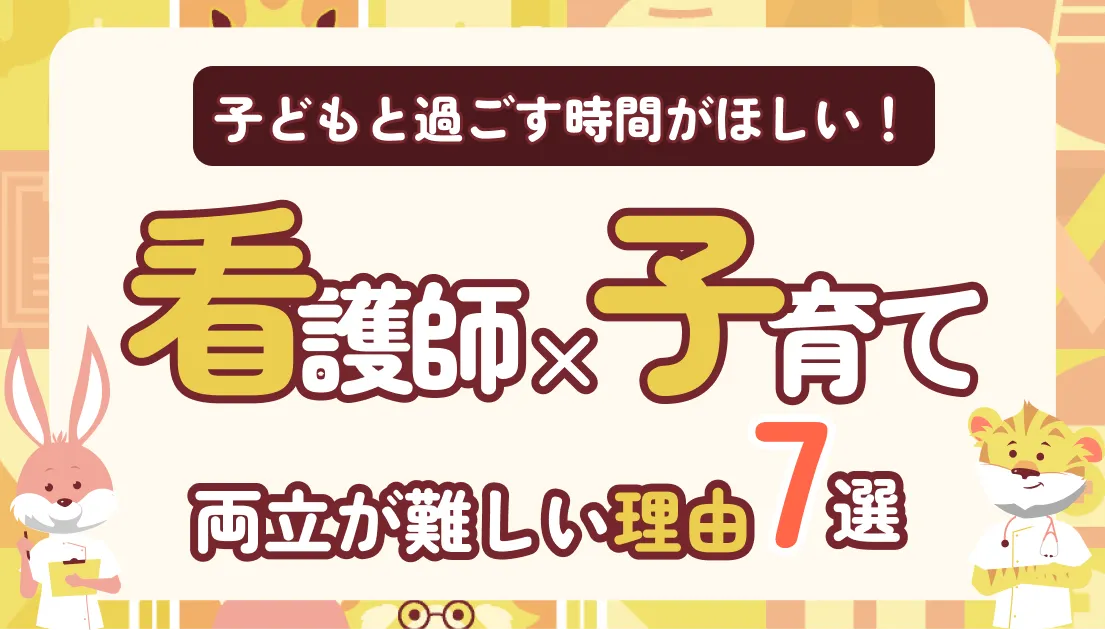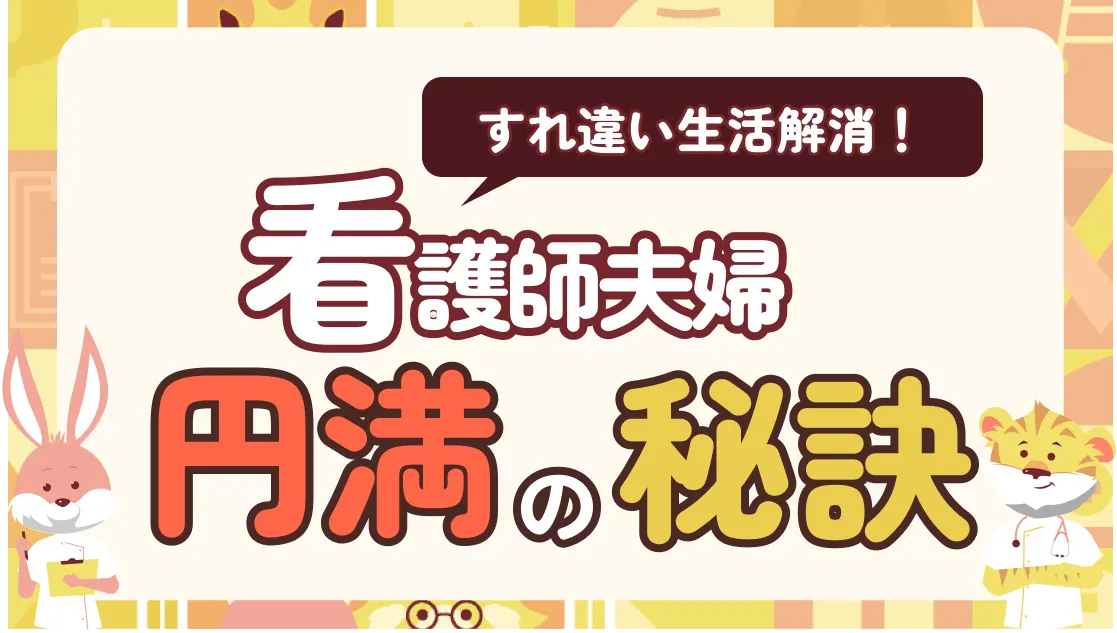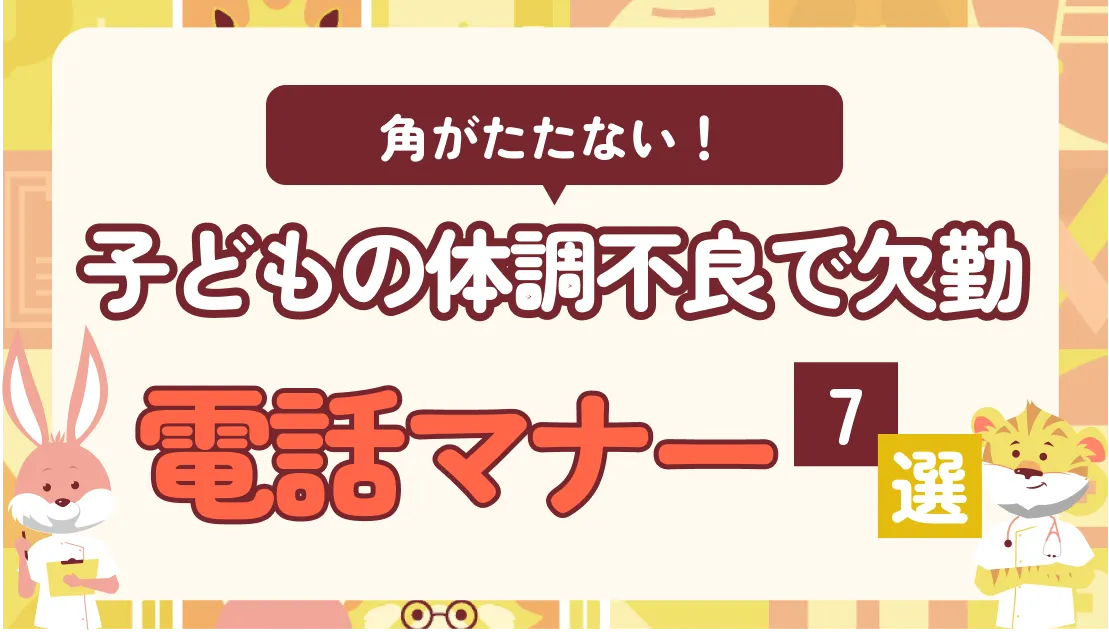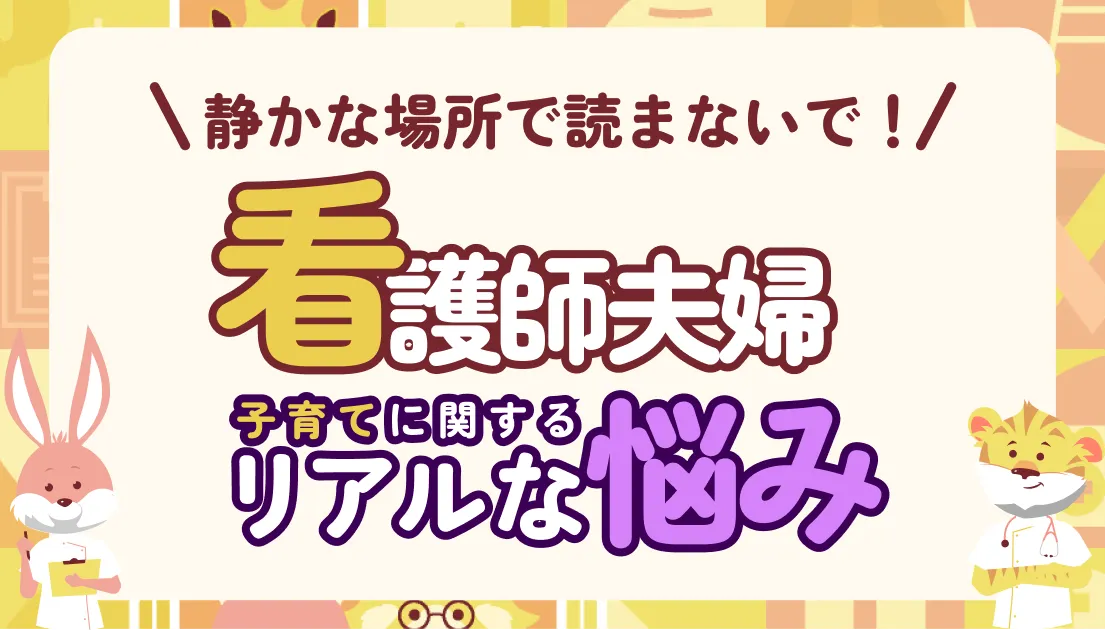看護師と子育ての両立はできる?難しい8つの理由と解決策まとめ【体験談あり】
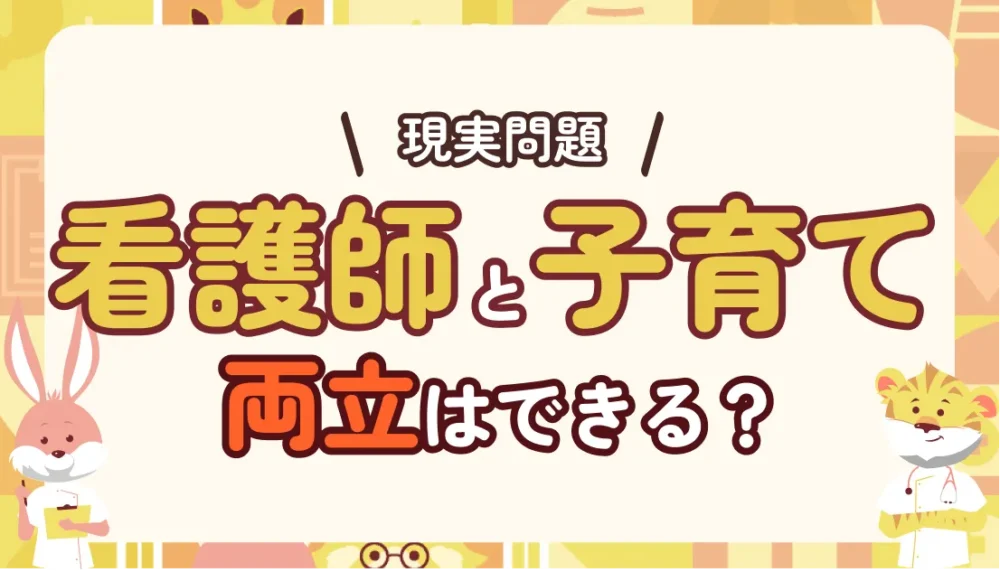
こんにちは!トラカンです!
今回は「看護師と子育ての両立はできるか?」についてお話しします!

看護師と子育ての両立ができる人って、どんな生活を送っているの?
両親の協力がないと両立なんて難しいって諦めている
子育てを犠牲にしないと看護師を続けるのは難しいよね
結論から言うと、看護師と子育ての両立はとてもハードですが、不可能ではありません
ただし、両立のためには工夫や働きやすい職場を選ぶことが欠かせません
この記事では、次の3つのポイントをもとに、無理のない両立方法をお伝えします
- 両立が難しい8つの理由
- 両立を実現する7つの工夫
- 両立しやすい職場17選
働きやすい職場を選びとちょっとした工夫だけで、両立するハードルがグッと下がります
両立しやすくなると心にも余裕が生まれ、仕事に対するストレスや「もう辞めたい…」と思うことも減るでしょう
もし今、両立に悩んでいるなら、まずは何か一つ行動を起こしてみてください!
動かないままだと、同じ悩みをずっと抱えたままになってしまいます
ぜひ最後まで読んで、看護師と子育てを両立するための第一歩を踏み出しましょう
【結論】看護師と子育ての両立はできるけど、かなりハード…
看護師と子育ての両立は可能です
実際、両親ともに常勤看護師で子ども4人の先輩も働いています
高度急性期の病院で働くママナースや、シングルファーザーの先輩看護師もいます

周りでも頑張っている先輩がいると、安心しますよね
ただ、両立にはそれなりの負担や厳しさもあります
日々の忙しさに加えて、予測不能なことも多いのが現実です
だからこそ、無理なく続けるための工夫が必要です
このあと、両立が難しい理由と、そして乗り越えるための工夫を紹介します
今まさに悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです
看護師と子育ての両立が難しい8つの理由
看護師と子育ての両立が難しい理由は、以下の8つです
- 理由1:子どもと過ごす時間が確保できない
- 理由2:乳飲子を置いて出勤しないといけない
- 理由3:キャリアアップ優先だと子育てが厳かになる
- 理由4:残業が続くと家事・育児が二の次になる
- 理由5:翌月の予定が立てにくい
- 理由6:せっかくの休日も潰れることが多い
- 理由7:学校や保育園との時間調整ができない
- 理由8:体力的に限界を感じている
理由1:子どもと過ごす時間が確保できない
子どもと過ごせる時間が足りないと感じる人は多いです
看護師の勤務が不規則で、生活リズムが子どもと合わないことが原因です
例えば、子どもが寝る時間から夜勤に出て、明けで帰宅したときにはすでに保育園へ…
日勤の残業が長引いて、帰宅が21時になる日もあります

子どもの顔を見ていない日が続いていたこともありました
ただし、こうした毎日は珍しくなく、多くの人が経験しています
休日出勤も多く、子どもと休みを合わせるのが難しいという声もよく聞きます
子どもと過ごしたい気持ちと生活のための仕事の間で悩む看護師は少なくありません
理由2:乳飲子を置いて出勤しないといけない
深夜勤の前は本当につらいと感じる人が多いです
ぐずる子をなんとか寝かしつけて、仮眠もほとんど取れないまま出勤…

勤務が始まる前からすでにクタクタなんですよね
出発直前に子どもが泣き出し、パートナーに預けて家を出る夜勤は特につらいです

あの瞬間の罪悪感は今でも忘れられません
夜勤免除の申請やシフト調整を相談できる職場ならまだ救いがあります
ただし、そうした雰囲気すらない職場もあり、悩みを抱えたまま働くケースもあります
理由3:キャリアアップ優先だと子育てが厳かになる
キャリアアップを目指すなら、子育てと両立するのは簡単ではありません
というのも、仕事に使える時間が限られているからです
独身のころは休日でも研修や看護研究に参加し、資格取得のために他県へ行くこともできました

独身ってだけでフットワーク軽いんですよね
一方で子どもがいると、たとえ時短勤務でもお迎えに間に合うかどうかの毎日です
休日は子どもと過ごしながら、平日にたまった家事をこなすだけで終わってしまいます
キャリアアップに充てられる時間はほとんどありません
キャリアを優先しすぎると、子どものことをパートナーに任せきりになる現実もあります
理由4:残業が続くと家事・育児が二の次になる
職場や部署にもよりますが、残業が多くてなかなか帰れないこともあります
日勤なのに帰宅が20時を過ぎた日もありました
朝は前残業で8時前には病棟入り…
1日の半分近くを職場で過ごす日が続くと、家事や育児はどうしても後回しになります

こんな生活が続いて良いんだろうか、とモヤモヤしていた時期もありました

なんのために働いているのか、わからなくなりますよね
理由5:翌月の予定が立てにくい
シフトが出るのはいつも月末ギリギリという職場も多いです
28日から31日あたりに出ることも…
そのせいで家族とのお出かけや、子どもの行事の予定が立てにくくなります
予定の中心が仕事になりがちで、柔軟に動けないことも悩みの種です
理由6:せっかくの休日も潰れることが多い
休日であっても急な勤務変更や、研修会への参加をしないければいけないこともあります
急に夜勤になった日には、翌日の予定も崩れます
子どもと外出する予定でも、夜勤明けの体調ではキャンセルせざるを得ないことも…
さらに、休日に看護研究があれば参加は避けられません

研究チームで集まるなら、誰かが休みを返上しないと成り立たないんですよね
結局、せっかくの休みも仕事で1日終わることもよくある話です
理由7:学校や保育園との時間調整ができない
不規則な勤務が続くと、保育園や学校との時間調整が難しくなります
これも看護師と子育ての両立を難しくする要因のひとつです
特に子どもが小さいうちは、保育園のお迎えや送りの時間に悩まされます
朝は7時すぎに出発し、時短勤務でも帰宅は18時すぎという日が続くと疲労困憊…
夜勤が絡む日は家を空ける時間も長く、家族の協力なしでは回らなくなります

とにかく毎日をこなすだけで精一杯になってしまいますよね
理由8:体力的に限界を感じている
看護師と子育ての両立は一にも二にも体力勝負です
これまで挙げた理由からも、かなりハードな日々であることが伝わってきます
最初は気力で乗り切れても、徐々に疲労がたまり、現実の厳しさに直面することも…
特に入園したては毎週風邪をひき、まともに仕事ができません
保育園に迎えに行き、小児科を受診し、翌日は休まざるを得ない日も出てきます

休みが続くと、職場にも申し訳なくて、気持ちも焦ってしまいますよね
ようやく3か月ほどで慣れてきたと思ったころに、今度は独り立ちのタイミングです
重たい患者や新しい業務を任され、責任が一気に増えてプレッシャーも大きくなります
残業も増え、帰宅後は予習や復習にも追われ、疲れが抜けにくくなっていきます
復帰後半年ほどで限界を感じ、離職を選ぶ人も決して少なくありません
看護師と子育てを両立するためにできる7つの工夫
看護師と子育てを両立するためにできる7つの工夫は、以下の通りです
- 工夫1:子育て支援制度を活用する(※職場が運営)
- 工夫2:子育て支援制度を活用する(※自治体が運営)
- 工夫3:院内保育や学童保育を利用する
- 工夫4:通勤時間の見直しをする
- 工夫5:家族の理解や協力を得る
- 工夫6:時短家電を使う
- 工夫7:子育てしやすい部署や職場へ移る
工夫1:子育て支援制度を活用する(※職場が運営)
まずは制度を活用し、仕事の負担を減らすことから始めましょう
職場の代表的な子育て支援制度は、以下の通りです
- 制度1:短時間勤務(時短勤務)
- 制度2:深夜業(夜勤)の制限
- 制度3:所定外労働(残業)の免除
- 制度4:時間外労働(残業)の制限
- 制度5:育児休業
- 制度6:子の看護休暇
時短と夜勤免除を利用するだけで、保育園の迎えや準備が楽になりました
また、夕方から夜にかけて子どもと一緒に過ごせて良かったと今振り返っても思います

子育て支援制度について、もっと詳しく教えてください!
詳しくは、誰も教えてくれない子育て支援制度6選|ナース夫婦は知らないと損で解説しています
工夫2:子育て支援制度を活用する(※自治体が運営)
せっかくなので、自治体(国や地方)が運営する子育て支援制度についても紹介します
育児の負担を減らすなら、以下の制度を検討しましょう
- 制度1:一時預かり事業【自治体】
- 制度2:病児保育【自治体・民間】
- 制度3:養育支援訪問【国】
- 制度4:ファミリー・サポート・センター【自治体】
- 制度5:放課後児童クラブ【自治体】
- 制度6:子育て支援パスポート【自治体】
- 制度7:地域子育て支援拠点事業【自治体】
病児保育は子育て看護師の救世主的ですよね

でも、私の地域の病児保育は1日に5人しか利用できないので激戦です
経済的な負担を減らすなら、以下の制度を検討しましょう
- 制度1:児童手当
- 制度2:児童扶養手当
- 制度3:子ども医療費助成制度
- 制度4:自立支援医療(育成医療)
- 制度5:高等学校等就学支援金制度
- 制度6:高校生等奨学給付金
- 制度7:高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)
給付金についてもチェックしておきましょう
日本の社会保険は徴収は強制(給料から天引き)ですが、給付は申請です

つまり、制度を知らない人が損する仕組みです
この機会に制度について学び、必要な支援を受けられるようにしましょう
詳しくは、子育てナースは確認必須|意外と知らない国・地方自治体の子育て支援制度一覧で解説しています
工夫3:院内保育や学童保育を利用する
勤務先の病院に院内保育があるなら、利用を検討しない手はありません
院内保育の最大のメリットは、送迎の時間がなくなることです
忙しい朝や慌ただしい夕方に送迎がないだけでも、時間と気持ちに余裕が生まれます
また、急な発熱などで呼び出しがあってもすぐに駆けつけられる点は親として安心です

子どもが近くにいるというだけで、心なしか安心できます
子どもが小学生になったら、学童保育の利用も現実的な選択になります
帰宅後に一緒に宿題をする余裕がない家庭も多いため、学童で済ませてくれるのは助かります
工夫4:通勤時間の見直しをする
意外と見落とされがちですが
通勤時間が長いと子育てとの両立はグっと難しくなります
保育園の送迎は毎日のことですし、急な呼び出しにも対応が求められます
特に入園したばかりの時期は、毎週のように新しい風邪をもらって帰ってきます

電話が鳴るたびに、またか…とため息が出てしまいますよね
呼び出しが重なると、職場と自宅の往復だけで精一杯になります
通勤時間を見直すだけでも、心と時間に少し余裕が生まれます
工夫5:家族の理解や協力を得る
看護師と子育ての両立には、家族の協力が欠かせません!
あなた自身が無理をして体調を崩しては、元も子もないからです
パートナーに保育園の送迎をお願いしたり、子どもが理解できる年齢なら夜勤のことを説明することも大切です
どうしても家族だけで両立が難しい場合は、両親や知人の協力を得る場面も出てきます

私の先輩は子どもが4人で、両親ともに常勤看護師です
両親だけでなく、近所の知人にも助けてもらいながら、何とか続けていると話していました
工夫6:時短家電を使う
仕事に子育てと忙しい日々が続くと、どうしても家事にまで手が回りません
洗濯物は山積み、部屋の隅にはホコリがたまり、洗い物も溜まっていることがよくあります

すべて自分でやらなければと頑張っていた時期もありましたが、正直ムリでした
そこで割り切って時短家電を導入しました
洗濯物は乾燥まで全自動、お掃除ロボットに食洗機の3つです
これだけで負担が減り、1日に2時間ほど余裕が生まれました
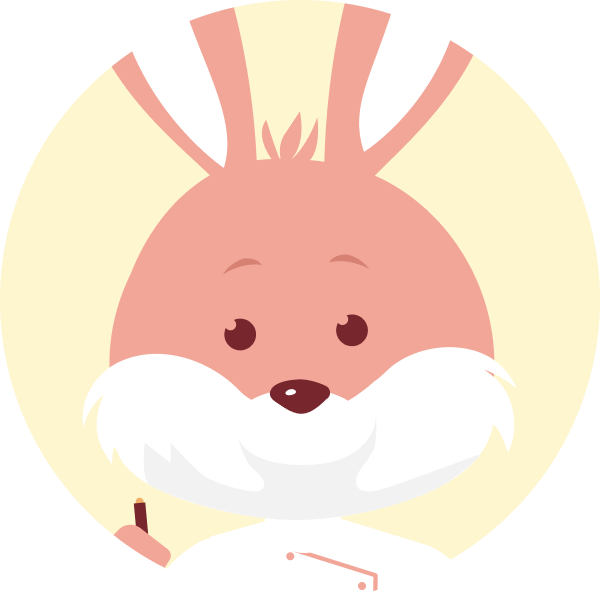
2時間あれば、子どもに本を読んだり、一緒に宿題をしたりする時間が作れますね
少し高価な買い物でしたが、買って後悔はしていません
工夫7:子育てしやすい部署や職場へ移る
そもそも今の職場が子育てしやすい環境かどうか見直すことが大切です
難しい場合は部署異動や転職も検討しましょう
職場自体が子育てに向いていなければ、自分の努力だけではどうにもなりません
たとえば「シフト調整ができない」「残業が常態化している」職場は早めに離れることをおすすめします

どんな職場なら良いのでしょうか?

夜勤のない部署や夜勤免除が認められる職場が理想です
それか、あえて夜勤専従にする選択肢もあります
まずは上司に相談しましょう
相談に応じてもらえない場合は、迷わず転職しても問題ありません
夜勤免除については、こちらの記事にて▼
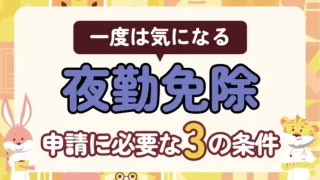
夜勤専従については、こちらの記事にて▼
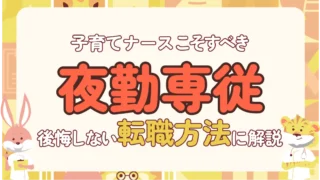
子育て看護師の転職事情については、こちらの記事にて▼
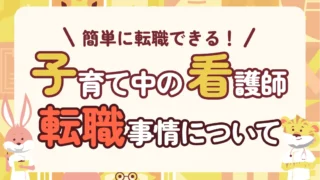
看護師と子育ての両立がしやすい職場17選
看護師と子育ての両立がしやすい職場は、以下の17つです
- 職場1:病院の外来
- 職場2:透析室看護師
- 職場3:クリニック
- 職場4:訪問看護
- 職場5:訪問入浴
- 職場6:検診センター
- 職場7:デイケア、デイサービス
- 職場8:介護施設
- 職場9:保育園
- 職場10:放課後デイサービス
- 職場11:産業看護師
- 職場12:健康保険組
- 職場13:行政機関
- 職場14:保健師
- 職場15:治験コーディネーター
- 職場16:大学や専門学校の先生
- 職場17:フリーランス看護師【※新しい働き方の提案】
なんだかんだで夜勤のない職場が子育てしやすいのは間違いありません
でも、どんなものがあるか聞かれると、パッと出てきませんよね
そんな人は、【日勤限定】あなたに合う転職先はどれ?子育てしやすい職場17選と現役ナースの声を読んでください!
夜勤ありきと思われがちですが、実は日勤だけの職場もたくさんありますよ!
子育て看護師の働き方事例|3つ紹介
この章では、子育て看護師の働き方事例を3つ紹介します
- 事例1:夜勤免除+時短勤務を活用した事例
- 事例2:深夜勤を月8回こなす事例
- 事例3:子どもの興味を活かした事例
事例1:夜勤免除+時短勤務を活用した事例
看護師Aさんは育休明けに夜勤免除と時短勤務で職場に戻りました

この働き方、もはやママ看護師のテンプレですよね(笑)
朝は保育園の開園に合わせて出勤し、夕方にはお迎えがあっても、一人で対応できます
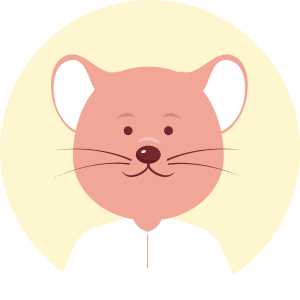
子どものそばにいられる安心感は、何よりも大きいです
夜勤がないことで、夜泣きや発熱にも柔軟に対応できます
家庭との両立がしやすいと感じているとのことです
その一方で、時短と夜勤免除により給与は減りました
それでも今は生活とのバランスを優先し、この働き方を選んでいるそうです
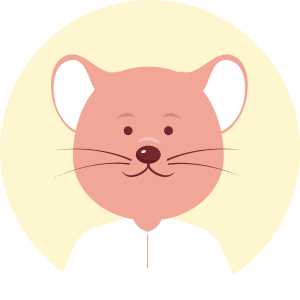
お給料は減ったけど、今は続けることが一番大事かなと思ってます
夜勤免除と時短勤務は、子育て中の看護師にとって、無理なく現場に戻るための現実的な選択肢のひとつです
事例2:深夜勤を月8回こなす事例
看護師Bさんは交代制で月8回ほど深夜勤をしています
夫は昼から夜遅くまでの勤務です
そのため、Bさんが深夜勤ならパパママのどちらかが家にいます
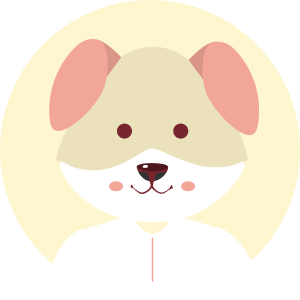
昼間家に誰もいないのが一番不安だったんです、深夜勤なら安心
育ち盛りの子どもがいると、生活費も教育費もバカになりません
経済的な理由からも夜勤は必須なのです
体力的に辛いこともありますが、準夜勤がないぶん、まだ生活リズムが整えやすいとのこと
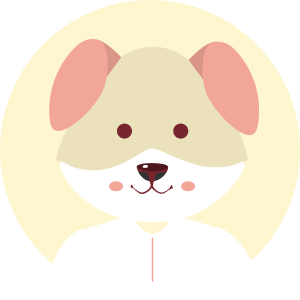
準夜勤より深夜勤のほうがリズムを整えやすいんです
夜勤明けの時間を活用して、学校行事や市役所での手続きもできます
家庭の事情や経済的な背景をふまえたうえで、あえて夜勤をするのも選択肢の一つです
事例3:子どもの興味を活かした事例
看護師Cさんは、平日8:30〜15:15の短時間勤務で働いています
小学生の息子は好奇心旺盛です
そして、両親の方針は「やってみたいことは何にでも挑戦させる」です

興味のあることは、まずやらせてみるって決めてます
息子が選んだのは体操、ボルダリング、そしてドラムでした
Cさん家では「歩いて通える場所であること」が唯一の条件
習い事は放課後や週末にまとめて、送迎の負担をなるべく減らしています

ちなみに体操とボルダリングは同じ施設で、ドラムは小学校の帰り道に寄れるんです
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 出勤の有無 | 日勤(8:30〜15:15) | 日勤(8:30〜15:15) | 日勤(8:30〜15:15) | 日勤(8:30〜15:15) | 日勤(8:30〜15:15) | 休 | 休 |
| 子どもの習い事 | 体操(16:30〜18:00) | 学童(放課後〜17:30) | ボルダリング(16:30〜18:00) | 体操(16:30〜18:00) | 学童(放課後〜17:30) | ボルダリング(16:30〜18:00) | − |
子どもは大好きなことに取り組め、Cさんも子どもを一人にさせずに済むので満足とのことです

子どもが習い事を楽しんでくれると罪悪感も減るし、助かってます
ただし、月謝の負担は大きく感じているようです

正直、習い事代のために働いてる気もします(笑)
それでも今だけの大事な時期と前向きに捉えながら、仕事と育児をうまく両立しています
子育て看護師にもできる3つの夜勤対策【経験談あり】
子育て看護師にもできる3つの夜勤対策は、以下の通りです
- 対策1:夜勤免除の申請
- 対策2:夜間保育の利用
- 対策3:あえての夜勤専従
対策1:夜勤免除の申請
心身の健康を保つためにも、夜勤免除の申請を検討してみましょう
特に乳幼児期は夜間の授乳が多く、夜勤と重なるとパートナーへの負担が大きくなります

泣く子どもを置いて出勤するのは、精神的にも辛いですよね
生活リズムが乱れ、疲労が積み重なれば、体調を崩すのも時間の問題です
一方で夜勤免除をしてもらえれば、日々の生活に安定します
子どもと同じペースで過ごせることで、夜もそばにいてあげられる安心感があります
さらに体力的な負担も減り、仕事と育児の両立もしやすくなるでしょう
詳しくは、【夜勤免除】子育てナースが申請すべき法律に基づいた3つの理由と却下時の対処法で解説しています
対策2:夜間保育の利用
夜勤は負担だけど、子どもが小さいうちに稼ぎたい親も多いです
そんな人は、夜間保育を利用すると良いでしょう
詳しくは、夜間保育ってどうやって預ける?!失敗しない選び方や子どもへ悪影響がない理由を解説で解説しています
対策3:あえての夜勤専従
あえて夜勤専従を選ぶ選択肢もあります
現在の私がこれです

夜勤だけなので、生活リズムが一定で体への負担は少ないです
給与面でも、夜勤手当や割増金があるので効率よく稼げます
子育てナースにおける夜勤専従については、子育てナースは夜勤専従に向いている⁈意外な理由と後悔しない転職方法で解説しています
子育て看護師の転職事情!簡単に転職できる4つの理由
簡単に転職できる4つの理由は、以下の通りです
- 理由1:子育ての経験が重宝される職場がある
- 理由2:看護師が引くて数多
- 理由3:臨床現場以外にも需要がある
- 理由4:転職サポートが充実している
子どもが居るからといって転職での評価が下がることはあり得ません
むしろ看護師だからこそ、どんな職場に行っても重宝されます
詳しくは、子育て看護師でも簡単に転職できる!4つの理由と転職成功のコツまとめで解説しています
看護師と子育ての両立に関するよくある3つの質問
看護師と子育ての両立に関するよくある質問についてお答えします
- 質問1:夜勤との両立は不可能でしょうか?
- 質問2:復帰できるか不安です…
- 質問3:転職前の志望動機や面接対策の方法がわかりません…
質問1:夜勤との両立は不可能でしょうか?
お子様の人数や家族の協力体制、経済状況などによって事情は大きく変わります
また、勤務先の夜勤体制によっても負担の感じ方も異なります
ただし、絶対に無理というわけではありません
実際、私の先輩は4人の子を育てながら、夫婦ともに常勤看護師として働いています

ちょっとパワフルすぎですよね!
子育て支援制度などをうまく活用すれば、両立も不可能ではありません
質問2:復帰できるか不安です…
ブランクがあると、復帰するだけですでに大変です
その上、子育てもあるため、不安になる気持ちはわかります
特に技術や知識の変化が激しい医療業界では、復帰の壁を感じる人は少なくありません
そんな人は、ナースセンターの復職支援を利用するのオススメです
復職支援では、以下の研修が受けられます
- 現場さながらのシミュレーション
- 最新情報の提供
- 相談員への復職相談 など
詳しい内容は、各都道府県ナースセンターに確認してください
参考:日本看護協会
質問3:転職前の志望動機や面接対策の方法がわかりません…
以下の記事で詳しく解説しているので、ご覧ください
子育て看護師である私や先輩の実体験をもとに書いています
そのため、今まさに今悩んでいる人に刺さる内容になっているかと!
志望動機については
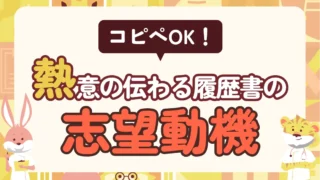
面接マナーについては
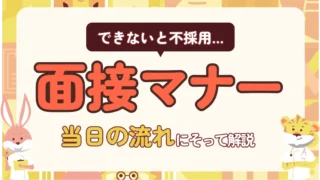
子育て看護師が面接で聞かれる質問は
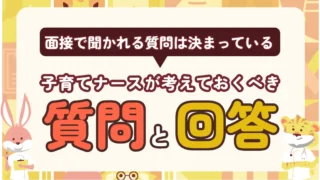
面接時の身だしなみについては
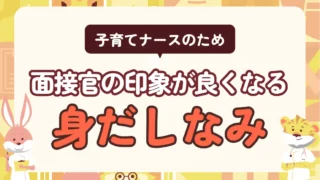
まとめ:看護師と子育ての両立はできる!
今回は「看護師と子育ての両立が可能か否か」について解説しました
看護師と子育ての両立は大変です
しかし、不可能ではありません
実際、先輩看護師は、以下のような工夫をして乗り越えています
- 工夫1:子育て支援制度を活用する(※職場が運営)
- 工夫2:子育て支援制度を活用する(※自治体が運営)
- 工夫3:院内保育や学童保育を利用する
- 工夫4:通勤時間の見直しをする
- 工夫5:家族の理解や協力を得る
- 工夫6:時短家電を使う
- 工夫7:子育てしやすい部署や職場へ移る
これらの工夫を取り入れるだけでも随分改善されるでしょう
社会資源や人脈を駆使してなお両立が難しいなら、今の職場自体が問題です
その職場でいくら工夫をしても自分一人でなんとかできることは限られます
そんな時は、あなたに合った職場へ転職することも考えましょう

でも、そんな都合よく子育てしやすい職場は見つからないよ…
それなら看護師転職エージェントを利用して、スマートに転職しましょう
エージェントを使った転職の流れについては、エージェントを使った看護師転職の流れ5ステップ|採用までの最短ルートを解説で解説しています
子育てしながら看護師として働くのは本当に大変…
だからこそ、今回の記事が一人でも多くの子育て看護師に届いてほしいです
ブログ記事をシェアしたり、SNSで取り上げたりしていただけると、トラカン先生がめちゃくちゃ喜びます
では、また次回の時期で会いましょう!